この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
事業経営をしていると個人と法人を問わず、家族を従業員として雇うことは少なくありません。特に起業時など事業規模が小さいときほどその傾向は強いでしょう。
このように家族を雇うと問題になってくるのが「給与の金額」です。個人事業主であっても法人であっても、税務調査でポイントになりやすいので、その仕組みや注意すべき点についてよく理解しましょう。
この記事では 個人事業主のケースと法人のケースを分けて、それぞれ家族に対する給与で必要な手続きや気を付けるべき点について解説します。
個人事業主と家族への給与
個人に課税される所得税ですが、個人で事業を行う場合たいていは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のどれかに該当します。事業を家族が手伝うことはよく見られますが、その家族に給与を払ったら経費になるのでしょうか。まずは所得税における個人事業主と家族従業員の関係を見ていきましょう。
所得税法における家族の給与
原則の話から始めると、所得税法では個人事業主が生計を一にする家族に支払った給与は必要経費として認められません。これは同居か別居かに関係なく、その家族がどのように生計を維持しているかの実態によります。つまりまったく独立している子供等の場合は必要経費として認められるという事です。
先ほど「原則」と書きましたが、 個人事業主で青色申告を選択している場合、税務署へ届出することで、事業専従者として働く家族の給与は必要経費として認められます。また白色申告の場合は専従者控除という定額の所得控除があります。
専従者給与と専従者控除
個人である程度の規模の事業を行うなら青色申告にしたほうが節税面でメリットが大きいので、大体の個人事業主は青色申告を行っています。
この青色申告にはいくつかのメリットがありますが、その中でも大きな2つのメリットがあります。ひとつは「青色申告特別控除」でもう一つが今回のテーマである「青色事業専従者給与」です。
先ほど「生計を一にする家族に支払った給与は必要経費として認められません」と言いましたが、青色申告の事業者は一定の要件を満たせば家族への給与が必要経費として認められます。
要件は次に3つ全てを満たさなければなりません。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

最初に2つの要件は特に難しいことではありませんが、最後の要件が問題になりがちなポイントとなります。一概に言えませんが、法人と比べ個人事業所主は必要経費算入の裏付けとなる帳簿や証憑の不備が多いため、専従者給与が否認されるケースが散見されます。
また名前のとおり「本当に専従していたのか」という点も税務調査で指摘されやすい事項です。
青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署へ提出しなければなりません。
支払う金額も届け出るので、もし増額などする場合も変更届を速やかに提出します。この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっていて、その内容は税務調査時のポイントとなるので注意しましょう。
白色申告の専従者控除は定額の控除なので、青色専従者給与より帳簿等の要件は簡単だと言えます。事業等所得から控除できる金額は次のうちの低い金額です。
- 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
青色申告に比べ要件は緩いのですが、専従者としての条件は同じなので、「その年を通じて6月を超える期間申告者の営む事業に専ら従事している」という点には注意を払いましょう。

個人事業主で税務調査のときのポイント
先ほども少し触れましたが、税務調査で否認されないポイントの一つが「専ら従事している」です。税務調査で否認され裁判まで至った例をみても解釈が難しいものです。
極端な例を挙げると、「事業を始めたばかりで配偶者が別に働いている」ケースと、軌道に乗った事業で「妻はほとんど家事に専念していた」ケースで、必要経費として認められない否認が目立ちます。
また事業専従者給与で問題になるのが「不相当に高額ではないか」という点で、任せている仕事の内容を鑑みて、「普通に使用人を雇った場合の給与」と比べて明らかに高額であれば否認される可能性が高いのです。
これらの点を踏まえて税務調査に備えるために、「勤務実態を残す」ことを第一に考えましょう。日々の伝票など調査時に確認される帳票に専従者の足跡を残すことが重要です。もう一点が、もし同じ業務で他人を雇用したときの給与を想定し、それから逸脱しない範囲の給与額にしておくことです。後述する法人役員と比較して支給額に対する調査の目は厳しいことを知っておきましょう。
銀行口座のお金がなくなっていく恐怖法人の代表者と家族の雇用
法人を設立し家族を雇い給与を払うには2つの方法が考えられます。一つは法人の取締役に就任させて役員報酬を払う方法で、これが一般的なやり方と言えるでしょう。もう一つが一般の従業員と同じ雇用契約を交わして給与を払う方法です。
同じことのように見えますが、法律上の解釈や税務調査の注意点が違ってきますので、それぞれの方法について見ていきましょう。
法人の役員報酬
法人の取締役に対して支払う報酬は給与とは性質が異なり、この点を理解することが重要になります。従業員に支払う給与は雇用契約に基づく「労働の対価」として支払うのに対して、役員に対して支払う役員報酬は「株主が会社経営を委任したことに対する対価」で、本来は仕事内容に対して文句を付けられる筋合いのものではありません。
しかし家族に役員報酬を支払っていると、税務署目線では「お手盛りで多く払っている」と思われがちです。
現在の法人税制上、少なくとも一定の要件を満たさないと損金算入出来ないようになっています。その要件とは以下のいずれかに当てはまるもの。
一つ目の定期同額給与がほとんどの同族会社で適用されている支給方法です。特に届出など必要なく、決算終了後に形式的であったとしても株主総会と取締役会を開催し、そこで役員報酬の上限と各取締役に支払う役員報酬を決め(議事録は必須です)、あとは決められた報酬額を変えることなく支給するだけです。
つまり決めた役員報酬を業績が大幅に上がったからといって、期中で役員報酬を上げることが出来ません。上げた場合はその金額は法人税法上損金算入が認められず、申告時に所得に加算しなければなりません。ただ業績が急激に悪化するなどの場合は減額に関しては認められることがあります。
二つ目の事前確定届出給与は支給の仕方を事前に税務署に届けるやり方で、特に意味のある方法ではありません。簡単に言うと「夏と冬にボーナスのように貰いたい」という支給の仕方を事前に届出るだけのものです。
三つ目の業績連動給与ですが、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことです。業績連動給与を損金計上するには、「報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである」「有価証券報告書に記載・開示している」「通常の同族会社以外である」という3つの条件を満たす必要があり、同族会社にとっては縁遠い支給方式です。
これが想定しているものは、外部からプロ経営者を雇い業績上昇のインセンティブを支払うようなケースで、多くの中小同族会社では採用することはないでしょう。

家族の社員雇用と給与
法人の役員報酬はいろいろな制約があり面倒に感じるかもしれません。では家族を役員としてではなく従業員として雇った場合はどうなのでしょうか。
この場合は「個人事業主の専従者給与」と同じ注意が必要になります。建前上は家族であろうが他人であろうが「労働の対価」で支払うべき従業員の給与なので、職務内容や一般従業員に比べ不当に高い(と税務署に指摘される)金額は否認される可能性が高くなります。
また同族会社の場合は経営者の家族は「みなし役員」と認定されることもあり、その場合賞与などの損金算入が認められない恐れもあります。
みなし役員は他人であっても「法人の経営に従事している者」という点で認定される可能性があります(例えば共同設立者で一方が従業員の身分でいるようなケース)。しかし税務調査では家族に視点が向きますので、社員雇用とはいえ注する必要があります。
税務調査と過大役員報酬
税務調査において役員報酬が問題になるのは主に2つの点です。一つは先ほど解説した「定期同額給与」などの基準を満たしているかで「形式基準」と言います。これは難しい要件ではありませんが、問題になるのは「役員報酬が過大(高すぎる)」なのかです。
過去の判例で一番多いのが、ほとんど役員としての勤務実態がないことが認定されたケースで、これに関しては従業員の勤務実態と別に考えなければなりません。
つまり役員とは「株主が会社経営を委任する」存在なので、少なくとも定期的に取締役会を開いており、会社の重要な意思決定に参画していたという証拠があれば税務署と戦うことは出来ます。
一方で難しいのが「実質基準」といわれる「同業他社の役員報酬と比較して高くないのか」という点です。しかし非常勤の取締役なら指摘されても仕方ないのですが、 常勤役員であれば相当高い役員報酬でない限り争う余地は残っています。これらの点は「いくら以上な大丈夫」という明確な金額がないので、顧問税理士などとよく相談したうえ決めるようにしましょう。
まとめ
個人事業でも法人事業でも、家族の雇用と支払う給与には注意を払わなければ、思わぬ追徴課税に会う恐れがあります。
税務署サイドの先入観として「家族を特別扱いしている」という思いが多分にあるが故のことですが、もしそんな事実があるとしたら一般従業員から見ても不公平感を感じ、士気の低下につながってしまうので、経営者としては注意を払いたいデリケートな問題と言えるでしょう。
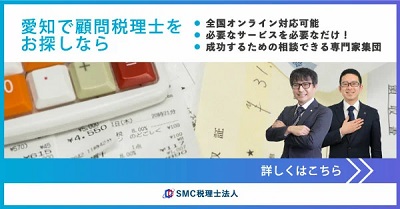

















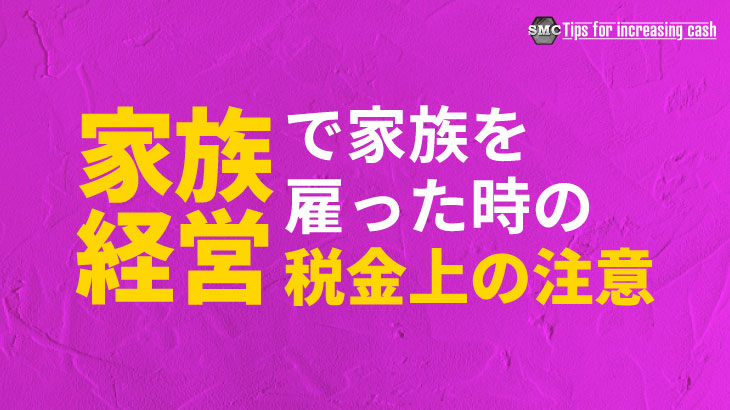
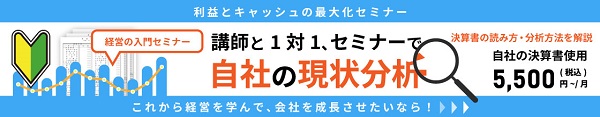



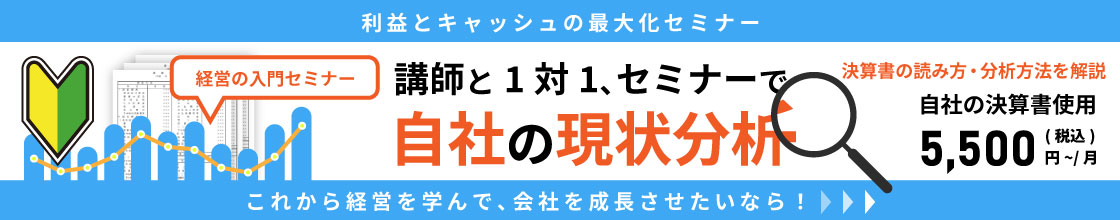






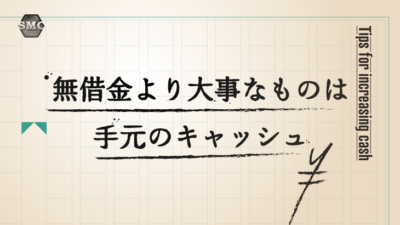

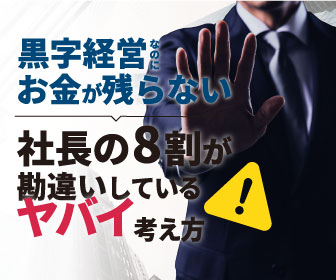















とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説-150x150.jpg)
